虫とあそぼう
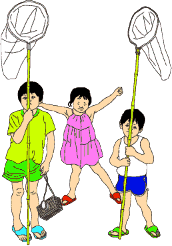
昆虫はそれぞれ自分たちの住みやすい場所で生活しています。
昆虫と出会うには、昆虫たちの生活場所、生活方法、活動時間などを知らなくてはなりません。
自分のまわりにどんな昆虫がいるか、また公園、雑木林、畑、田んぼなど、環境によって昆虫の種類がどう変わっていくかを知りましょう。
昆虫の種類
カブトムシ・クワガタムシ
雑木林で樹液さがしをしよう!
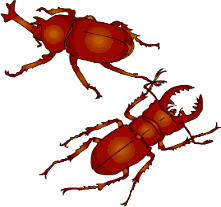
カブトムシ・クワガタムシは、日本だけでも8000種はいるという甲虫類に属す。
カブトムシ・クワガタムシは、木の樹液が食べ物なので、樹液がでているクヌギやコナラなどの木に集まる。樹液というのは、木の葉で作られた糖が幹を通っていく途中で幹の傷口からにじみでた甘酸っぱい液のことである。雑木林でクヌギやコナラの木を見つけたら、樹液のでている木をさがそう。
木を見つけたら、足の裏で幹をドンとけると、葉の上や枝で休んでいたカブトムシやクワガタムシがポトリと落ちてくるかもしれない。
カブトムシ・クワガタムシも夜行性なので、夜か明け方にいけば、樹液を吸っている姿を見つけやすくなる。また、昼間は木の根元の落ち葉の下にもぐっていることがよくある。
チョウ
通る道で待ちぶせよう!
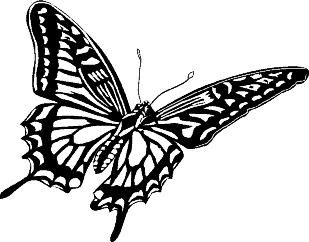
チョウの採取は、むしあつい晴れの日の9時~12時ごろが最良である。
チョウのくる場所は、花の咲いているところや樹液のでているところ、谷川や水たまり、雑木林の日だまり、見晴らしのよい山腹、尾根などさまざまだ。
木立のあいだや谷川にそった道を歩いていると、大型のクロアゲハが目の前をよこぎったりすることがある。こんなときは、あわてて追いかけずにしばらく待とう。”蝶道”といって、おなじコースをまた飛んでくるだろう。ゆっくり、気長に待っていよう。
花のまわりは、チョウ採取の最高のポイントになる。花の蜜を吸いにくるチョウは、種類によってめざす花がきまっているので、それぞれのチョウが好む花を調べておくとねらったチョウが採取しやすくなります。
トンボ
すばやく1回で勝負しよう!
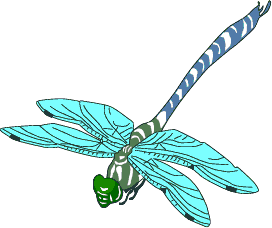
トンボは、近くに森や野原がある井家沼、湿地、田んぼ、水のきれいな川などにいる。風のない晴れた日の日中がもっとも活動する時である。
トンボの種類は、世界に5000種、そのうち日本にいるは約180種。日本最大のトンボはオニヤンマである。
トンボは目がいい上に、特に大型のヤンマ類は飛ぶ力も抜群。網をすばやく振る練習をしてから出かけよう。補虫網の柄はしならない木製の一本ざおがよく、網は風きりのいいメッシュのナイロン製が最良である。
オスのトンボをつかまえたら、おなかにひもをつけて飛ばしていると、メスのトンボが近づき、メスのトンボにひもをつけて飛ばせば、オスのトンボが近づいてくる。どちらも簡単にとらえられる。これを「トンボつり」という。
セミ
鳴き声で姿を見つけよう!

セミと一口にいっても何種類もおり、体長、形、はねの色、鳴く時間なども種類によってちがう。セミとりをする前に、まず代表的なセミ6種類の特徴をおぼえよう。
- ニイニイゼミ
- 小さくて平べったいセミ。はねのもようが木肌に似ているので見つけにくい。「ニイニイ」と小さく鳴く。
- アブラゼミ
- 体は黒く、はねは茶褐色。一番よく見かける大型のセミ。「ジーン」と連続して鳴く。
- ツクツクボウシ
- はねは透明で体は黒い。「ツクツクボウシ」または「オーシーツクツク」と鳴く。
- ミンミンゼミ
- はねは透明。体は緑色で黒いはん点がある。「ミーンミンミン」と鳴く。
- ヒグラシ
- 6月末から10月ごろまであらわれる。はねは透明。体はうすい緑色をし、褐色のもんがある。早朝と夕方、「カナカナカナ」と鳴く。
- クマゼミ
- 体長約47ミリ。日本最大のセミ。関西、四国、九州、沖縄にいる。大声で「シャー、シャー、シャー」と鳴く。
セミの声は鳴きはじめが小さく、だんだん大きな鳴き声になってくる。大きな声をだしている最中がつかまえるチャンスである。